久度神社由緒略記
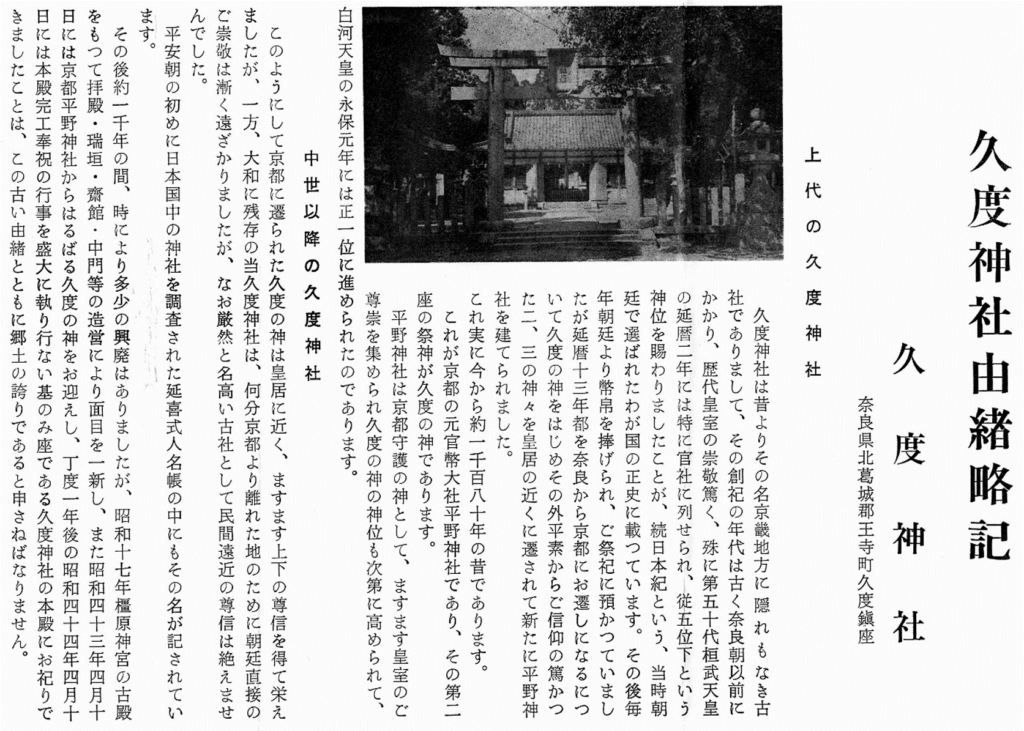
御由緒略記 解説
古代の久度神社
久度神社は古より今の奈良県北葛城郡王寺町久度に隠れも無き古社であり、その創祀の年代は古く「延喜式神名帳」では平群群の鎮座であるが、現在の王寺町久度四丁目の久度神社に比定される。史料上は「続日本紀」、延暦二年十二月丁巳条、平群群久神を従五位下に叙し官社になすとの記述がその所見であります。その後平安遷都に伴い今の京都山城の国平野祭神四社に移祀されることとなり、「続日本後記」「延喜神祇式」に散見する久度神はこの平野神社の祭神となった久度神であり、移祀後も京の都の守護の神として朝廷から厚く祀られていたことが分かり、白川天皇の永保元年には正一位に叙されることとなりました。
中世以降の久度神社
このようにして京都に祀られた久度神は当時の皇居にも近くますます上下の尊信を得て栄えることとなりましたが、大和の国に残された久度神社は朝廷直接のご崇敬からは遠ざかることとはなりましたが、依然として名高い古社として史料上に名を残し、時として久度庄と呼ばれ現在の葛下川を南端として大和川北域周辺であったり、久度神社の所蔵する「春日曼荼羅」の箱書きには「文明八年(1476年)廣瀬群久度郷とあり、史料上からも当初は平群群に属していたものの、その後の神威により、廣瀬群(現在の広陵町)との結びつきも強かったものと考えられます。中世以降、久度神社を中心とした農民たちの「宮座」が存在したことや久度地区に建設された王寺駅など、久度神等のご祭神は地域住民の精神生活上の支えとなり、地域の生活の向上と広域の発展の中心となって現在に至ります。
久度神社のご祭神
久度大神 竈の神、火の元の神
八幡大神 寿命、幸運の神
住吉大神 水運、交通の神
春日大神 子孫繁栄の神
※久度大神は桓武天皇の母である和史(高野)新笠所縁の神、他の祭神は崇敬者の時代の要請により合祀された神々である
出典:久度神社由緒略記(資料提供 久度神社)
鳥居にかかる扁額(へんがく)「徳維馨(とくこれかおる)」について

仁徳天皇が夕暮れ時に多くの民の竈(かまど)から煙が上がっているのを見て、凶作に当たって、自らの行った租税を免ずる善政効果を納得されたという話があるそうです。徳とは為政者(いせいしゃ:政治を行う人のことを指す)の徳のある政治のことで、徳維の維は徳と下の馨(かおる)という漢字を強調する言葉で、馨とは、心地よい笛の音が広く響き渡ったり、竈で黍(キビ)を調理するときにでる香ばしい良い香りが広く漂っていくような様子を表すそうです。よって、この3文字の意味は為政者が行う善政が、笛の音や黍の焼く良い香りが広く広がっていくような様子を表す言葉と考えられます。
また、扁額は建物の内外や門・鳥居など高い位置に掲出される額、看板であることから、書かれている文字はその建物や寺社名であることが多いが、久度神社に掛かる扁額はそうではなく、久度神社に創立等に深く関わった方の思いのようなものが書かれており、珍しい扁額となっている。
(出典:観光ガイド教育書籍)
